血便・下血とは
 血便(けつべん)とは、便に血液が混じっている状態を指します。これは、口から肛門までの消化管のどこかから出血しているサインです。出血した部位によって便の色が異なります。
血便(けつべん)とは、便に血液が混じっている状態を指します。これは、口から肛門までの消化管のどこかから出血しているサインです。出血した部位によって便の色が異なります。
- 鮮血便:
鮮やかな赤い血が混じった便で、肛門や直腸など、お尻に近い部分からの出血が考えられます。排便後にトイレットペーパーに血が付く、便器が真っ赤になる、といった場合も含まれます。 - 暗赤色便:
黒っぽい赤や赤黒い色の便で、大腸の奥の方や小腸からの出血が疑われます。 - 粘血便:
血液と粘液が混じった便で、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)や感染 性腸炎などが疑われます。
下血(げけつ)とは、広義には口から肛門までの消化管から出血した血液が肛門から排泄されることの総称です。便がなくても血液そのものが出る場合も含まれます。
一般的には胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を指します。上部消化管で出血した血液が便として体外に出るまでに時間がかかるため、胃酸などによって酸化され、黒っぽい色になります。特にコールタールのように真っ黒でドロドロとした便は「黒色便(タール便)」と呼ばれます。出血量が多い場合は、酸化する前に排出され暗赤色になることもあります。
血便・下血は消化管のどこかに異常があるサインであり、健康な消化管から通常出血は起こりません。少量であったり一時的であっても、何かしらの異常が隠れている可能性があるため注意が必要です。
血便・下血の症状チェックリスト
血便や下血は、目で見てすぐにわかることもあれば、注意深く観察しないと気づかないこともあります。
以下のような症状が一つでも見られる場合、消化器内科や胃腸科、肛門科などの専門の科がある病院やクリニックへの受診を検討する必要があります。
- トイレットペーパーで拭いたら血が付いていた
- 排便時に出血があった、または便器が血で染まった
- 真っ黒な便(タール便)が出た
- 下痢のようなゆるい便に血が混じっていた
- 便に粘液が付着している
- 便が細くなった
- 便に血が混じっていることが肉眼で確認できる
- 健診で便潜血検査が陽性になった
また、血便・下血に加えて、以下のような随伴症状がある場合は、より一層注意が必要です。
血便・下血の主な原因の例
血便や下血は、消化管のさまざまな部位からの出血によって引き起こされる可能性があり、その原因疾患は多岐にわたります。
以下に主な原因疾患の一覧を示します。
下部消化管からの出血(血便の原因として多い)
上部消化管からの出血(下血の原因として多い)
- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍:黒色便(タール便)の原因として多いです。
- 胃がん:黒色便の原因となります。
痔からの出血と決めつけて自己判断してしまうのは危険です。これらの原因を特定するためには、専門的な検査が必要となります。
次に、どのような検査が行われるのかをご説明します。
当院でできる血便・下血に対する検査
血液検査
 貧血の度合いや炎症の有無などを調べます。
貧血の度合いや炎症の有無などを調べます。
内視鏡検査
血便・下血の原因を特定する上で最も重要かつ精度の高い検査です。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
 肛門からスコープを挿入し、大腸全体を直接観察します。大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの診断に非常に有効であり、病変部からの組織採取(生検)や、ポリープの切除もその場で行える場合があります。血便の色だけでは痔か大腸がんかを区別できないため、大腸内視鏡検査による原因特定が重要です。多くのクリニックでは、苦痛に配慮した検査を提供しています。
肛門からスコープを挿入し、大腸全体を直接観察します。大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの診断に非常に有効であり、病変部からの組織採取(生検)や、ポリープの切除もその場で行える場合があります。血便の色だけでは痔か大腸がんかを区別できないため、大腸内視鏡検査による原因特定が重要です。多くのクリニックでは、苦痛に配慮した検査を提供しています。
胃内視鏡検査(胃カメラ)
 黒色便(タール便)の場合に、食道、胃、十二指腸からの出血を調べるために行われます。
黒色便(タール便)の場合に、食道、胃、十二指腸からの出血を調べるために行われます。
カプセル内視鏡検査、小腸内視鏡検査
胃カメラや大腸カメラで診断がつかない小腸からの出血が疑われる場合に検討されます。
血便・下血に対する治療法
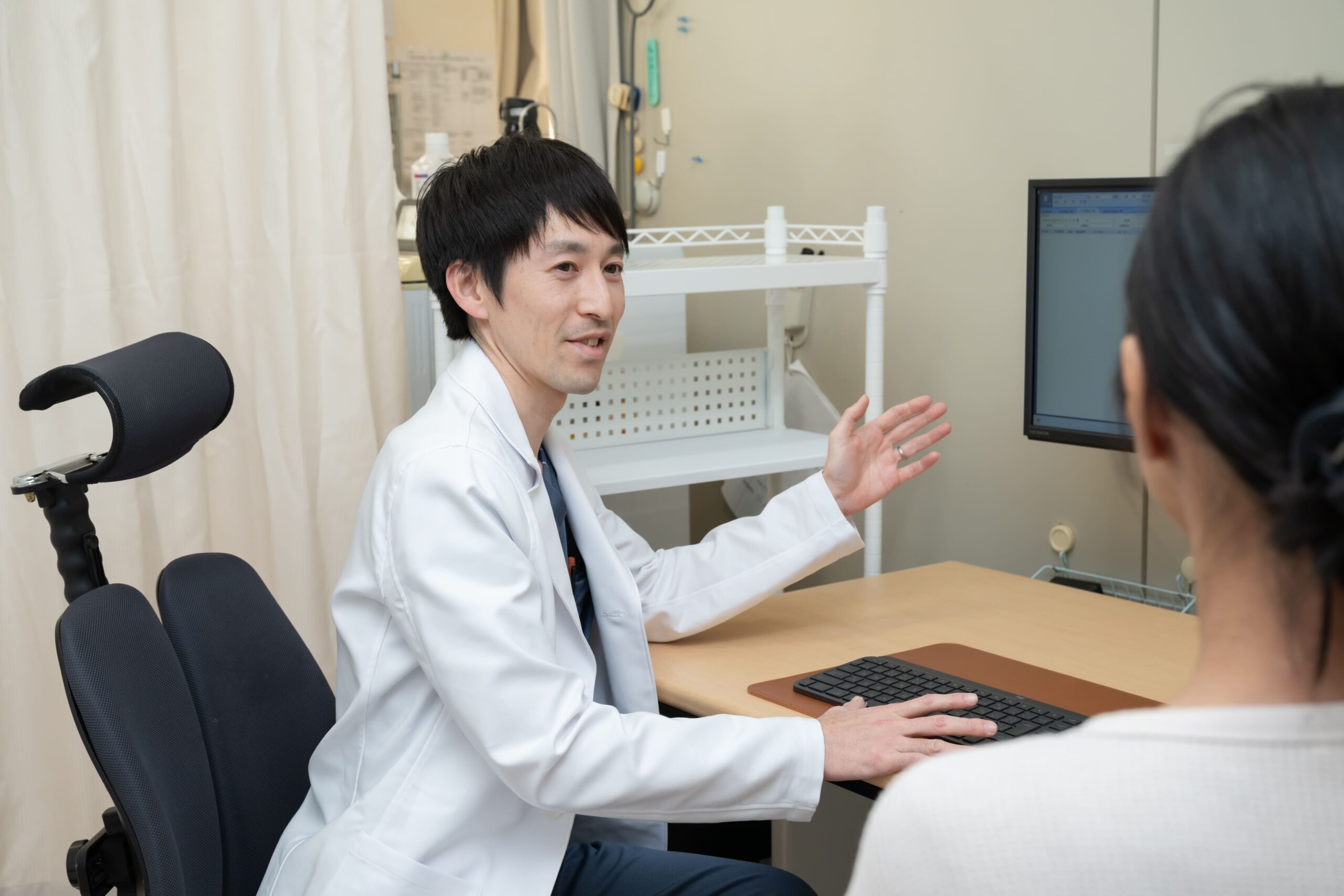 血便や下血に対する治療法は、その根本的な原因疾患によって大きく異なります。
血便や下血に対する治療法は、その根本的な原因疾患によって大きく異なります。
自己判断で市販薬を使用したり、様子を見たり、特に痔からの出血だと思い込んで放置したりすることは、重篤な疾患を見逃す危険があるため絶対に避けましょう。血便・下血を認めた場合は、速やかに消化器内科や胃腸科、肛門科などの専門の科がある病院やクリニックを受診し、正確な診断に基づいた治療を受けることが非常に重要です。
考えられる主な治療法は以下の通りです。
- 内視鏡的治療:
大腸ポリープが見つかった場合は、内視鏡検査中にその場で切除することが一般的です。
出血が続いている病変に対して、内視鏡を用いて止血処置を行うこともあります。 - 薬物療法:
潰瘍性大腸炎やクローン病といった難病や、感染性腸炎、虚血性腸炎など、炎症や感染が原因の場合は、炎症を抑える薬や抗菌薬などによる治療が行われます。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の場合は、胃酸分泌を抑える薬やピロリ菌の除菌治療などが行われます。 - 外科的治療:
大腸がんや進行したポリープ、薬物療法で改善しない一部の疾患に対しては、手術が必要となる場合があります。
痔の場合も、程度によっては手術が検討されることがあります。 - 保存的治療:
痔や軽度の裂肛など、原因によっては外用薬の使用や生活習慣の改善(便秘の解消など)によって症状が緩和されることもあります。
血便や下血は、体からの大切な「火災報知器」のようなサインです。小さなサインでも見逃さずに、専門の科で原因を調べ、早期に適切な治療を受けることで、多くの疾患は良好な経過をたどります。血便・下血の症状がある場合は、決して軽視せず、お早めに医療機関にご相談ください。









